・朝からだるい、疲れている
・やる気が出ない、会社へ行きたくない
・1日中、眠い
・集中力がなくなる
そんな症状で悩んでいませんか?
新年になってからというもの、会社へ行きたくないと感いている方は7割もいるそうです。
かくいう自分も覚えがあります。
ずっと休みなら良いのに、と思いつつ生活のために働かなくちゃ。けれど仕事中も眠くて集中力が欠けて、ミスを連発して困ってしまう。ずっとこのままだったらどうしよう、なんて不安も湧いてくる。そんなモヤモヤを解消できるように、正月うつの原因と対策を解説していきます。
正月うつになる4つの原因

どうしてこんなにも朝、起きれないのだろう?
体が動かない、頭が重い、元気が出ない…。
気力が出ないから仕事へ行くのがとても辛い…。
そのような正月うつと呼ばれる症状の主な原因は以下の4点です。
1.精神的なストレス
2.肉体的な疲労
3.胃腸の疲れ
4.睡眠の乱れ
それぞれ詳しく見ていきましょう。
1.精神的なストレス
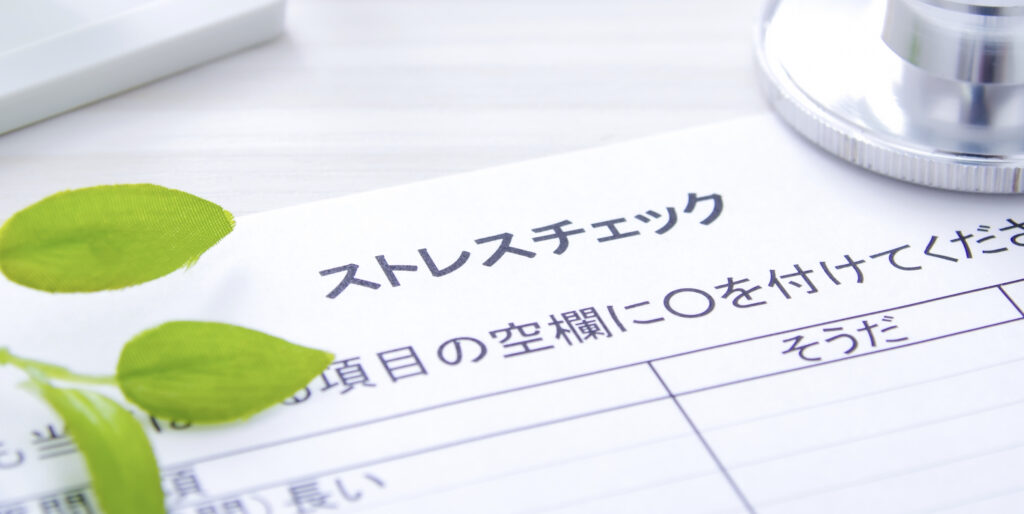
12月に入るとイベントが目白押し。
仕事は年末進行で多忙になり、一方でX’masや大掃除、年始の準備、年越しイベントや帰省、親族の集まりなど色々と重なってきます。
親しい友人や親族とのお付き合いでも、普段と異なる環境での興奮や緊張が続くことで、知らず知らずのうちに気疲れが溜まっているのです。頑張る人ほどその傾向は強いといえます。
2.肉体的な疲労

イベントや帰省などでの遠出や外出により、普段より体に負荷がかかっています。
長距離ドライブをすれば同じ姿勢が続く筋肉の凝りや目の疲れ、列車などを利用すれば混雑している駅や車内で過ごすストレスもあります。
外で過ごす時間が長ければ寒さで筋肉は冷えて固まってしまうので、血行が悪くなりさらに筋肉疲労が積み重なるという悪循環にはまります。
動いている間は気持ちが興奮しているのであまり感じないかもしれませんが、帰宅して緊張が緩むと蓄積された疲れがドッと出てきたと実感することも多いでしょう。
3.胃腸の疲れ

年末年始は何かと食生活が乱れがちです。ごちそうを前にお酒も美味しく進むでしょう。昼間からTVを見ながらおやつを食べる機会が増えるし、外出すれば美味しそうな食事処へ寄りたくなります。
楽しくて美味しい時間と引き換えに、胃腸は働きっぱなしです。次から次へと入ってくる食物の消化活動で大忙し。その結果、便秘や下痢が続いたり、お肌が荒れたりしてきます。
新陳代謝も落ちてくるので体が重く感じられて、動くのがおっくうに感じてしまうでしょう。
4.睡眠の乱れ

連休中はどうしても生活リズムが乱れがちになります。夜更かししたり、午後まで寝ていたりと不規則な生活をしていた結果、体内リズムが狂い睡眠の質を落としているのです。睡眠不足は思考力・判断力に影響を及ぼします。
さらに冬は日照時間が少ないため幸せホルモンのセロトニンが減少しがちです。夏の日照平均は約15時間に対して冬は約10時間ですから、セロトニンの生成量にも大きな差が出てきます。
セロトニンの量が減少すると、睡眠ホルモンであるメラトニンが生成されなくなり、睡眠の質が落ちていくのです。
★セロトニンとは
トリプトファンから作られるホルモンで喜怒哀楽、恐怖、驚きなどの感情を司どり精神を安定させる。起床で分泌が始まり脳に覚醒状態を促す、就寝すると分泌がとまる特徴を持つ。
★メラトニンとは
体内時計の役割を持ち、副交感神経のスイッチを入れて自然な眠りに誘います。
睡眠の質をあげ、夜中など途中で目が覚めにくくなる効果をもたらします。
他に高い抗酸化作用で新陳代謝を促したり、疲労回復の役目も持つ。
正月うつを吹き飛ばす3つの対処法

朝から憂鬱になりがちな正月うつ。毎日を楽しく過ごすためにも早く解消したいですよね。
以下にその対処法を具体的にあげていきます。
1.生活リズムを整える
2.胃腸をリセットする
3.良質な睡眠をとる
詳しくみていきましょう。
1.生活リズムを整える

体の調整日を作りましょう。
起床、食事の時間を平日と同じか1時間程度の誤差に近づけます。起床後は太陽の光を浴びてセロトニン分泌を促しましょう。そして朝食を摂りましょう。炭水化物は脳のエネルギー源ですから、ご飯やパンを食べて脳の起床スイッチを後押しします。
また適度に体を動かすことも必要です。
TVを観たりゲームをしたり、本人はくつろいでいるつもりでも実は筋肉には負荷がかかっています。
ずっと同じ姿勢を続けていると、筋肉は緊張して硬くなり血行不良が生じて疲労物質が溜まります。それが肩こりや腰痛などの原因にもなるのです。
軽い散歩をしたり、買い物に出かけるなどして気分転換を図りましょう。適度な疲れは夜の入眠効果も高めてくれます。
ベッドの中へはスマホを持ち込まないようにして強い光を感じない環境を作ります。眠気を誘う副交感神経の作用はスロースターターなので、眠る前の1時間くらいは気分がリラックスする雰囲気作りをするといいでしょう。
2.胃腸をリセットする

胃腸が働きすぎで疲弊してくると、食べ物の消化や栄養吸収、老廃物の排出といった機能が低下します。胃腸の機能低下は便秘や下痢を繰り返し、免疫力の低下に繋がります。
そうなる前に食生活を改善して、胃腸が本来の働きを取り戻せるようにしましょう。
効果的な対策に以下の2つがあります。
1. 必要な栄養素を補充する 2. プチ断食をする
それぞれ詳しく説明します。
1.必要な栄養素を補充する

暴飲暴食のあとは代謝に必要なビタミン群や、消化を助ける食材を足すと良いでしょう。
●糖質を体内エネルギーに変換するビタミンB1
豚肉・生ハム・うなぎ・ごま・大豆
●体の代謝をサポートするビタミンB2
レバー・うなぎ・カマンベールチーズ・海苔・椎茸・アーモンド・納豆
●消化を促す食材
大根おろし、レモン、ゆず、カボス、山査子(さんざし)、陳皮(ちんぴ)
●セロトニンを増やす食材(トリプトファン&ビタミンB6)
カツオ・マグロ・大豆製品・乳製品・バナナ・サツマイモ・玄米
毎日の食事で意識的に使ってみてください。
同時にお腹を温める飲み物などを一緒に摂るようにすると、内臓の働きが良くなり消化力が上がります。乱れていた食生活で溜まってしまった胃腸の疲れと老廃物をデトックスして、スッキリ爽やかな体調を取り戻しましょう。
2.プチ断食をする

食事を消化するのにかかる平均時間は、胃が4〜5時間、腸が7〜9時間といわれています。そのため食事の間を14〜16時間くらい空けて胃腸を休ませてあげましょう。睡眠時間を組み込めば、わりと簡単にできます。
また一食だけ低カロリーの食品で済ませる、置き換えダイエットも効果的です。
酵素ドリンクやプロテイン、血糖値をあげない少量の食材にすれば胃腸への負担はかなり軽減されます。ダイエット効果も期待できて胃腸のリセット・デトックスができるので一石三鳥になりますね。
胃腸が整うと便秘や下痢をしなくなる、免疫力が上がる、血液が綺麗になる、肌の調子がよくなる、メンタルが安定するなど嬉しいことがたくさんあります。
腸内環境は常に変化しているので、定期的に行うことをおすすめします。
3.良質な睡眠をとる

かつて「睡眠負債」という言葉が流行ったくらい、日本人は慢性的な睡眠不足だと言われています。加えて睡眠の質まで落ちてしまうと様々な病気の原因になると知られています。
また腸が体に必要な成分や免疫細胞を作り出すのは夜中、睡眠中なのです。睡眠時間が少ないとその働きも阻害することになってしまいます。良質な睡眠を得るために、日常の中に取り入れていきたい習慣を紹介します。
1.日光浴セラピー 2.ぬるま湯入浴
それぞれ説明していきます。
1.日光浴セラピー

セロトニンは目が光を感じると起床スイッチが入って分泌を始めるので、起床後に太陽光の元でウォーキングをすると脳が覚醒して行動意欲を促進してくれます。
体が目覚めて活動量が増えれば、軽い筋肉疲労などで寝つきがよくなり睡眠の質が良くなります。
早朝ウォーキングが難しい場合は、カーテンを開けて室内で太陽光を15分くらい感じるだけでも構いません。あるいは通勤の時に日光浴を意識するのもいいでしょう。車内で太陽光を感じたり、日向を歩いたりしてヤル気スイッチを入れましょう。
2.ぬるま湯入浴

一日の疲れをとってリラックスするには、ぬるま湯が適しています。それは眠気を誘う副交感神経が好む温度が38〜40℃くらいのぬるま湯だからです。逆に42℃以上の熱いお湯は活動スイッチである交感神経を興奮させてしまうので、寝る前の入浴では避けた方が無難でしょう。
ぬるま湯にゆっくり浸かることで体の深部まで温まり、血行が良くなって筋肉や関節が和らぎ疲れをとってくれます。
また人体の構造上、体温が1度上がってから基礎体温に戻ると眠くなるようにできているので、温浴効果は肉体的にもスムーズな入眠に大きな役割を果たしてくれます。
正月うつ対策にアロマテラピーがおすすめ

なかなか改善できない心身の重苦しさを軽くする4つ目の手段として、アロマテラピーがおすすめです。
精油の効能は幅広く、消毒・殺菌・鎮静・免疫などに作用することは科学的にも解明されてきています。気持ちの切り替えを手軽にできるのもいいですね。
そんなアロマの活用方法について解説していきます。
1.精油とは 2.正月うつを和らげるアロマ 3.アロマの使い方
それぞれ詳しく見ていきましょう。
1.精油とは

植物の中にある芳香成分だけを抽出したものです。精油の力は実はパワフルで、脳にダイレクトに影響します。
脳は心身の変化を司る司令塔。その脳に精油の香りは0.6秒で届きます。視覚、触覚、聴覚、嗅覚、味覚の五感の中で嗅覚が一番早く情報を伝達できるのです。
香りを嗅ぐことで感情が変化するだけでなく、自律神経が整ったり、ホルモンの分泌を調整するなど体調の変化を促します。
フランスなどでは医師が処方箋を書いて治療薬としても使われています。日本ではごく一部の精油以外は薬としての認可を受けていませんが、その効能は医療の補完療法として活用されています。漢方と同じような位置付けですね。体の治癒力を自然に引き出すことで健康促進に役立てられるのです。
2.正月うつを和らげるアロマ

正月うつの代表的な症例別におすすめのアロマを紹介します。
- 元気が出ない ▶︎ ラベンダー・ローズウッド・ジュニパー・ゼラニウム
- だるい疲れ ▶︎ ユーカリ・レモングラス・マジョラム・ローズマリー
- やる気UP ▶︎ グレープフルーツ・ペパーミント・オレンジスイート
- 集中力UP ▶︎ ローズマリー・ティーツリー・ベルガモット・レモン
- 眠りが浅い ▶︎ ラベンダー・ネロリ・フランキンセンス・サンダルウッド
アロマの効能は多岐にわたります。症状に合わせて使い分けると自身の自然治癒力を促してくれるので、基礎体力アップに繋がります。自然パワーを上手に活用しましょう。
3.アロマの使い方

アロマは日常生活の中に取り入れやすいアイテムです。
その楽しみ方をご紹介します。
1.芳香浴
2.アロマバス
3.アロマトリートメント
アロマは香りを楽しむだけでも効果を感じられますし、肌に塗ればアロマの成分が肌から浸透して体に変化をもたらしてくれます。
好みの香りを選んだり、容器に凝ったりしてファッション感覚で楽しむのもいいし、体をいたわる時間は自分へのごほうびにもなります。ぜひ取り入れてみてください。
1.芳香浴

アロマポットやディフューザーなどに好みのアロマを数滴たらして香りを楽しみます。
お洒落な容器を選ぶとインテリアとしても楽しめていいですね。
外出先でも活用するなら、アロマペンダントを使ったり小瓶スプレーに入れて持ち運んだりすると手軽に楽しめます。
2.アロマバス

ぬるま湯に好みのアロマを4〜5滴入れてゆっくりと入浴します。
香りの効果と肌から浸透する効果の両方を感じられて心身ともにリラックスできます。
ぬるま湯入浴の効果も加わって、正月うつのストレスから解放されるでしょう。
3.アロマトリートメント

ホホバオイルやココナッツオイルなど植物オイル20mlに好みのアロマ4滴以内を混ぜて使います。
手足や気になる箇所へ塗り、その上から優しくマッサージします。
香りによる心のリラックス効果と、肌からの浸透で筋肉が緩んだり肌の調子を整える効果が期待できます。
★柑橘系アロマの中には光毒性作用を持つ物があります。紫外線に当たるとシミや炎症などの肌トラブルを起こす可能性があるので皮膚に使用する際には注意が必要です。
(例)ベルガモット・グレープフルーツなど
長引く正月うつで仕事が辛いと感じている人が、この記事を参考にしてハッピーな毎日に変化してくれたら幸いです。



コメント